2019�N12���ɒ����̕����Ō����s���̔x��������A2020�N1��7���ɂ��̌������V�^�̃R���i�E�C���X�iSARS-CoV-2�j���Ɠ��肳��܂����B���{�ł�2020�N1��16���ɏ������҂�������A1��27���ɂ͐V�^�R���i�E�C���X�ɂ�銴���ǁiCOVID-19�j���w�芴���ǂɎw�肳��܂����B
�����̊����Ґ��͖�1,320,000�l�A���҂͖�16,000�l�i2021�N8��24�����_�j�ł��B������V�^�R���i�E�C���X�̏��͎��X���X�ƕς���Ă����܂��̂ŁA���I�T�C�g�ŐV�������Ă����܂��傤�B
��w�E�u�w���
�i���{�����NJw��j�V�^�R���i�E�C���X�������Տ��Ή��E�_���E�Ǘ��
�i���������nj������j�V�^�R���i�E�C���X�����ǁiCOVID-19�j�֘A���ɂ����u�w�E�ψي��E�������
�V�^�R���i�E�C���XSARS-CoV-2�̃Q�m�����q�u�w����
�i2020�N�S�����_�j/(2020/7/16����)/�i2020�N10��26�����݁j/�i2021�N1��14�����݁j
�����E�`�d���̑�����R�����̕ω������O����� �V�^�R���i�E�C���X�iSARS-CoV-2�j�̐V�K�ψي��ɂ���
��P���i2020/12/22�j/�Q/�R/�S/�T/�U/�V/�W/�X/�P�O/�P�P/�P�Q�i2021/7/31�j/�P�R�i2021/8/28�j/�P�S�i2021/10/28�j
SARS-CoV-2�̕ψي�B.1.1.529�n���ɂ��āi��P��j�i2021/11/26�j
���{���Ȋw��G���F�V�^�R���i�E�C���X�����Ǔ��W�i2020�N11��10�����s�j
Principles of Epidemiology: Home|Self-Study Course SS1978|CDC
CDC ���O�q�����H�ɂ�����u�w�̌���(�p��)
SARS-CoV-2�V�K�ψي�(Spike�^���p�N���̕ψ�)
�ψي��̓���
N501Y�̕ψق�����ψي��]���������������₷���\���B�p�����A�t���J�Ŋm�F���ꂽ�ψي��ɂ��ẮA�d�lj����₷���\�����w�E���� �Ă���B
E484K�̕ψق�����ψي��]���������Ɖu��N�`���̌��ʂ�ቺ���� ��\�����w�E����Ă���B
��26��V�^�R���i�E�C���X�����Ǒ�A�h�o�C�U���[�{�[�h�i�ߘa3�N4��7���j�����S �V�^�R���i�E�C���X�����ǁi�ψي��j�ւ̑Ή���
���{�ŗ��s���Ă���ψي�
D614G�i���B�j2020�N1�����{���`���s�B�A���t�@���ɒu���ς��܂Œ����嗬���BSARS-CoV-2 D614G variant exhibits efficient replication ex vivo and transmission in vivo
[WHO label Alpha(�A���t�@��)]VOC-202012/01�iB.1.1.7 �p���j2020�N9��20�����`���s�B�f���^���ɒu�������܂Ŏ嗬���BN501Y�̕ψفB
[WHO label Beta(�x�[�^��)]501Y.V2�iB.1.351 ��A�t���J�j2020�N5���`���s�BE484K, N501Y�̕ψفB�����E�`�d���̑�����R�����̕ω������O����� �V�^�R���i�E�C���X�iSARS-CoV-2�j�̐V�K�ψي��ɂ��� �i��5��j�i2021/1/25�j
[WHO label Gamma(�K���}��)]501Y.V3�iP.1 �u���W���j2020�N11���`���s�BE484K, N501Y�̕ψفB �u���W���̃}�i�E�X�n��̏Z����76�����������Ă����Ɛ��肳��Ă����ɂ�������炸�A���̕ψي������s�B�������̑�����Ċ������N��������\�������O����Ă���B�����E�`�d���̑�����R�����̕ω������O����� �V�^�R���i�E�C���X�iSARS-CoV-2�j�̐V�K�ψي��ɂ��� �i��6��j�i2021/2/12�j
hCoV-19/Japan/IC-0824/2021�i�t�B���s���j2021/2/25�܂͕s��E484K, N501Y�̕ψق�L����B.1.1.28�n�����BVOC-202012/01���Ɠ��l�Ɋ����͂Ɋ֗^����P681H�̕ψق���B�t�B���s������̓����҂��猟�o���ꂽ �V�^�R���i�E�C���X�̐V�K�ψي��ɂ���
N501Y�̕ψق͂Ȃ���E484K�̕ψق�����ψي�R.12020�N12����{�ȍ~�����Ō��o�B�V�^�R���i�E�C���XSARS-CoV-2 Spike�^���p�N�� E484K�ψق�L����B.1.1.316�n���̍��������i2021�N2��2�����݁j�����E�`�d���̑�����R�����̕ω������O����� �V�^�R���i�E�C���X�iSARS-CoV-2�j�̐V�K�ψي��ɂ��� �i��8��j�i2021�N4��7�����݁j
[WHO label Delta(�f���^��)]B.1.617.2(�C���h)2020�N10���`���s�B���{�ł�2021�N3�`5�������o�B2021�N8�����_�̎嗬���BL452R�AD614G�AP681R�ψق�L����BE484�ɕψق�L���Ă���̂�B.1.617.1�B�ʏ�3�d�ψفi�C���h�̐��x���K���B�Ŋm�F����Ă���B.1.618�j�Ƃ͕ʁBSARS-CoV-2�̕ψي�B.1.617�n���̌��o�ɂ��āi2021�N4��26�����݁j �����E�`�d���̑�����R�����̕ω������O�����V�^�R���i�E�C���X�iSARS-CoV-2�j�̐V�K�ψي��ɂ��� �i��11��j�i2021�N7��17�����݁j
[WHO label Omicron(�I�~�N������)]B.1.1.529�i��A�t���J�j2021�N11���`2022�N��������f���^���ɒu������茻�݂̎嗬���B�f���^��������Ԋu���Z���i�Q�����x�j�����͂������B�ق��̕ψي����d�lj����X�N�͒Ⴂ�Ƃ݂��Ă���B
SARS-CoV-2�̕ψي�B.1.1.529�n���ɂ��āi��P��j�i2021/11/26�j/�i��Q��j�i2021/11/28�j/�i��R��j�i2021/12/8�j/�i��S��j�i2021/12/15�j/�i��T��j�i2021/12/31�j/�i��U��j�i2022/1/13�j/�i��V��j�i2022/1/26�j
SARS-CoV-2 B.1.1.529�n���i�I�~�N�������j�����ɂ��V�^�R���i�E�C���X�����ǂ̐ϋɓI�u�w�����i��1��j�F�������������Ԃ̌����i2022/1/5�j/�i��2��j�F�V�^�R���i���N�`�����ڎ�҂ɂ�����E�C���X�r�o�����i2022/1/13�j/�i��3��j�F�V�^�R���i�E�C���X���Ǐ�a���ۗ̕L�҂ɂ�����E�C���X�r�o�����i2022/1/27�j/�i��4��j�F�u�w�I�E�Տ��I�����i2022/1/28�j
��69��V�^�R���i�E�C���X�����Ǒ�A�h�o�C�U���[�{�[�h�i�ߘa4�N1��26���j�����S �V�^�R���i�E�C���X�����ǁi�ψي��j�ւ̑Ή���
�u�̂ǂ̒ɂ݂������v�u�k�o�E���o�ُ̈�͏��Ȃ��v�@�V�^�R���i�@�I�~�N�������̏Ǐ�̓����́H�i2022/1/15�j
�I�~�N�������̈���"BA.2"�ɂ��Č����_�ŕ������Ă��邱�Ɓ@�u�X�e���X�E�I�~�N�����v�̈Ӗ��Ƃ́H�i2022/1/29�j
�@��
�V�^�C���t���G���U�������ʑ[�u�@
�����ǂ̗\�h�y�ъ����ǂ̊��҂ɑ����ÂɊւ���@��
�E���I���
���I���
�i�����J���ȁj�V�^�R���i�E�C���X�����ǂɂ��������݂̂Ȃ��܌����̏��E�����̔�����
(���t���[)�V�^�R���i�E�C���X�����Ǒ��V�^�R���i�E�C���X�����Njً}���Ԑ錾�̊T�v�A��{�I�Ώ����j�A���{��������
���@�@�V�^�R���i�E�C���X�����ǂɔ����ā@�`��l�ЂƂ肪�ł�����m���Ă������`���N�`���ɂ��āE�����ƌٗp����邽�߂̎x����
WHO Coronavirus disease (COVID-19) Pandemic
���Ƃ̒�
�V�^�R���i�E�C���X�����Ǒ� ���Ɖ�c�̌������Ɖ�c�i2020/2/20~2020/5/29�j
�V�^�C���t���G���U�����L���҉�c�V�^�R���i�E�C���X�����Ǒ����ȉ�ȉ�i2020/7/6~2021/2/25�j
�V�^�C���t���G���U�������i��c��{�I�Ώ����j���ȉ�(2021/4/1~)�E�V�^�R���i�E�C���X�����Ǒ����ȉ�(2021/4/8~)
�V�^�R���i�E�C���X�����Ǒ�A�h�o�C�U���[�{�[�h�̎����������J���ȁ@�A�h�o�C�U���[�{�[�h�i2020/2/7~�j
�V�^�R���i�E�C���X�����ǂɊւ�����ƗL�u�̉�
��
NHK�@�V�^�R���i�E�C���X���݃T�C�g�ŐV�j���[�X�A�E�C���X�̓����E��̉��
�Ǐ�
�������m�F���ꂽ�Ǐ�̂���l�̖�W�O�����y�ǁB�����Ǐ�����M�E�P�E���ӊ��EႁE�k�o��Q�E���o��Q�E����Ɠ��ʂȂ��̂͂Ȃ��B�������Ă��Ǐo�Ȃ��l�������i4�����x�j�A�y�ǂł��}�ɏd�lj��i�x���j����P�[�X������B����҂��b�����̂�������d�lj����₷���B�x���̂ق��Ɍ��t�⌌�ǂ̏�Q������邱�Ƃ�����B�܂��T�C�g�J�C���X�g�[���ƌĂ��ߏ�ȖƉu�����ɏd�Ăȑ����Q���N��������A�}���ċz�����nj�Q�iARDS�j�Ƃ����d�x�̌ċz�s�S���N�������肷��B
�������Ԃ͂P�`�P�S���i��ʓI�ɂ͂T���j�B�������I�~�N�������͐��������Q-�R���A���I����V���ȓ��ɔ��ǂ���l���啔���ł���ƕ�����B�����͂ɏǏ�̏d���͊W�Ȃ����ǂ̂R���O���甭�nj�T�����炢�ɐl�ւ̊����͂������B�����҂̂W���͐l�ւ̊��������Ă��Ȃ��Ďc��̂Q�������X�N�̍������ɂ����đ����̐l�Ɋ��������Ă���B
�V�^�R���i�̏Ǐ�A�o�߁A�d�lj��̃��X�N�Ǝ�f�̖ڈ��́H(���ߌ��u 2021/7/25)
Incubation period of COVID-19: a rapid systematic review and meta-analysis of observational research
���Ö@
2021�N8�����݁A�d�lj����X�N�̍����y�ǎ҂Ɏg���Ă钆�a�R�̖�ȊO�͑Ώ��Ö@�̂݁B���ʂ��m�F���ꂽ�R�E�C���X��A�R���ǖ�Ȃǂ��g���Ă���B�m���鎡�Ö@��\���Ȑl�X�Ƀ��N�`���ڎ킪�ςނ܂ŁA��Õ��Ȃ��悤�Ɋ����Ґ��𑝂₳�Ȃ��헪���Ƃ�B
�Ǐ�A�\�h�A�o�߂Ǝ��Ác�@�V�^�R���i�E�C���X�����ǂƂ́H�@�����_�ŕ������Ă��邱�Ɓi2021�N5���j(���ߌ��u)
�V�^�R���i�E�C���X ���Ö�E���N�`���̊J�������܂Ƃ߁yCOVID-19�z�i2021/8/20�j
�V�^�R���i�E�C���X������COVID-19�f�Â̎������ ��6.2�������J���ȁi 2022 �N 1 �� 27 ���j
COVID-19 �ɑ�����Â̍l���� �� 8 �����{�����NJw��i2021�N7��31���j
�E�C���X����
�V�^�R���i�E�C���X�����Ǖa���̌����̎w�j2021�N6��4�� ��4��
COVID-19 �f�f�E���ÁE�������i2020.11.15�j
PCR����
polymerase chain reaction�i�|�������[�[�A�������jDNA�̈ꕔ�����������ď��ʂł������ł���B�E�C���X�����Ƃ͈Ⴂ�s�����E�C���X�����o�����B�܂����ʂ����邽�߁A���l�Ɋ���������̂ɏ\���ȃE�C���X�ʂ����邩���킩��Ȃ��B���{�ł͕ψق��ɂ����E�C���X������N����ς����̈�`�q�̈ꕔ�������̃^�[�Q�b�g�ɂ��Ă���B
PCR�����̊��x��30�`70���A���ٓx90�`99���ƌ����Ă���B���x�́A�z���𐳂��������ł���m���A���ٓx�͉A���𐳂��������ł���m���B���x���Ⴂ���ߗL�a�����Ⴂ�Ɛ��x���������߁A�������Ă���\�����������҂��������邱�Ƃ��d�v�B
�Ȋw[�H�w�E���w]���x�Ɠ��ٓx
����ŊȒPPCR�����yT�P�A�N���j�b�N�z�R�̌���
�R�͓̂���̃E�C���X���i�R���j��F�����Č������邽��ς����q�B�����p����B�זE�������B�R���ɍR�̂���������ƕs������������Ɖu�זE�̖ڈ�ɂȂ�B��Ɋ��������ɍ����IgM�Ɗ�������ɍ��ꏊ���i�Ɖu�j�ƌĂ��IgG�̓��ނ�����B�R�̂ɂ̓E�C���X�Ɍ��ʂ�������́A�S�����ʂ��Ȃ����́A�E�C���X�̎菕����������̂�3��ނ��E�C���X�ɂ���ē��ٓI�ɍ����B
�v�������B�R���i�E�C���X�̈ꕔ���j��Y�����������L�b�g�Ɍ��t��H�����āA�R���ƍR�̂����т��ƐF���ς�����ł킩��萫�����B�Ɖu���l�����Ă��邩�̌����̏ꍇ�A���ʂ�����R�̂������ł��邩�A������ނ̃E�C���X�̍R�̂ł͂Ȃ������ӂ���K�v������B
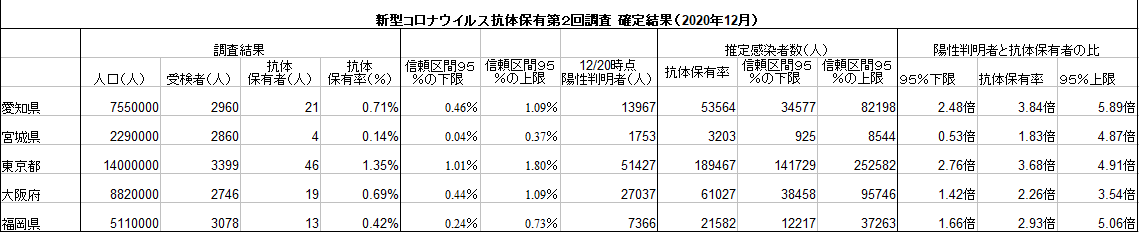
�R������
�R���̓E�C���X�₻�̔j�ЂȂǂ̍R�̂��ł��錳�B�C���t���G���U�̂悤�Ȑv���f�f�L�b�g�́A�����L�b�g�ɐl�H�R�̂����Ă���A�R���ƍR�̂̌��������o����B
���͕̂@�����ʂ����t�E���t�B��ʌ������ȈՃL�b�g
![]() ������A�ȈՃL�b�g�Ɩ��Ǐ�̏ꍇ�͑��t�Ō����͐�������Ă��Ȃ��B
������A�ȈՃL�b�g�Ɩ��Ǐ�̏ꍇ�͑��t�Ō����͐�������Ă��Ȃ��B
�\�h
���������̘A��
�a�����a�������r�o��ˁ��`���o�H���N����ˁ����h�偨�a�����c
���̘A���̂ǂ����ꂩ���ł��f����Ί����͗\�h�ł���
�a���F�a�C�̐����w�I�E�Ȋw�I�E�����I�ȗv���B�V�^�R���i�E�C���X�B
�a�����F���������q�����Ȃ��Ƃ��������邱�Ƃ��ł��A�������悯��Α��B�ł���ꏊ�B���ҁB
�r�o��ˁF���������q���h�傩��o��Ƃ��ɒʂ�g�̕��ʁB�ċz��E���o
�N����ˁF���������q���h��̑g�D�ɐN�����邽�߂ɒʉ߂���g�̕��ʁB�ċz��E���o
�����o�H�F���������q���r�o��˂��o�Ă���N����˂ɂ��ǂ蒅�����߂̎�i�B�i�G�A���]���j�����A�ڐG����
���h��F�����┭�a��h���͂̂Ȃ��l�⓮���B
��b����w�Ԉ�Ê֘A������(������3��): �W���\�h��T�[�x�C�����X�܂�
�����o�H
�����o�H�͐ڐG�����Ɣ����B�������₷�����i�R�̖��m���E���W�E���ځn�j�ł͔��ׂ������q�i�G�A���]���j���L�͈́E�����ԕY���A�G�A���]�����܂�C����Ċ���������B��Ȋ����o�H�͔i�G�A���]���j�����ŁA�ڐG�����͌���I�B
science Quantifying SARS-CoV-2 transmission suggests epidemic control with digital contact tracing
�V�^�R���i�̊����o�H�@���ܕ������Ă��邱�ƁA���܂ł��邱���i ��{�j�߁@2021/5/8�j
�k��a�@������}�j���A���i��6�Łj
���{�������w���c�[��Ver.3�i������̊�{���ډ����Łj
�V�^�R���i�E�C���X�����ǂɑ��銴���Ǘ��������i2021�N8��6���j
�����g��̗���
��҂������ɋC�t�����ɑ����̐l�ɍL���A����Ҏ{�݂��Ë@�ւŏd�ǎ҂��₷���Ɋ������A�ǏłĊ��������o�B�C�O�⊴�����X�N�̍����ꏊ���犴���̖h���ɂ����ꏊ�֍L����B
�ړ��E�s���������Ȏ�N�w�i10��㔼-50��j�ŃN���X�^�[�A�����g��B��N�w�͏d�lj����ɂ����̂Ŋ��������݉����₷���B
�������X�N�̍������ڂȐڐG�����H�X�i�����X�j�Ŋ������g��B�X���������Â炢���̗��R�Ń����N���킩��Â炭�����g���h���ɂ����B
���Ǐ�ł������͂�����_�A���̂悤�Ȑ����I�E�Љ�I���R�ɂ�芴�����c�����Â炭�A�����g��ɂȂ���₷���B�N���X�^�[�̘A�����N���邱�ƁB���ɑ�K�͂ȃN���X�^�[�i���K�N���X�^�[�j���N���Ă��܂��A��������2���I�ɑ����̃N���X�^�[�����܂��B
�N���X�^�[��������2021�N7��26�����_�i 7��25���܂ł̔�������j��45��V�^�R���i�E�C���X�����Ǒ�A�h�o�C�U���[�{�[�h�i�ߘa3�N7��28���j���J������
COVID-19 case-clusters and transmission chains in the communities in JapanScienceDirect 11 August 2021
�W�c�������₷������
�u���C�̈�������ԁj�v �u�����̐l�����W�v �u�ߋ����ł̉�b�┭���i���ځj�v�̂R�̖��i�R���j�B ���̑�́A �u���܂߂Ɋ��C���s���i�\�ł���Q�̕����̑����ɊJ����j�v �u�l�̖��x��������i�݂��̋������Q���[�g�����x������j�v �u�ߋ����ł̉�b�┭���Ȃǂ������i��ނȂ��ꍇ�̓}�X�N������E�Z���Ԃōς܂���j�v�N���X�^�[�����������ꏊ
�ڑ҂����H�X�a�@
�J���I�P�����H�X
�E��i��c�j
�X�|�[�c�W��
�o�X�c�A�[
����Ҏ{��
�ƒ��
�i���������nj������j�N���X�^�[����W
�������X�N�����߂₷�����
���������e����l����[��ɂ���Ԉ��H
��l����}�X�N�Ȃ��ł̉�b
�d�����x�e����
�W�c����
�������ċz���^��
���O�ł̊����̑O��
�l�̈ړ��Ɋւ��镪�ȉ�琭�{�ւ̒� �ߘa�Q�N�X���Q�T���i���j
�������X�N�����܂�u�T�̏�ʁv
���������e���l���Ⓑ���Ԃɂ���Ԉ��H
�}�X�N�Ȃ��ł̉�b
������Ԃł̋�������
���ꏊ�̐�ւ��
�ڐG�����\�h��
�ڐG�����͕���̂ɂ��Ă����E�C���X����ŐG��A���̎�ŕ@��ڂ����G�邱�Ƃɂ���Ă�����B���A���R�[���ɂ���w���ŁA�s���Ȏ�Ŋ��G��Ȃ��A�}�X�N��ዾ�����ĕ����I�ɐG��Ȃ��悤�ɂ���Ȃǂ̑���B
��w�q��
���
�Ό����g����15�b�ȏォ���ĐB�w��A�w�̊ԁA�e�w�͐c�����������ʁB���̌�悭�������B��r��h�~�̂��߁A�悭�������ӂ�����Ċ������E�ʂ߂肪�Ȃ����炢�Ό��A���悭���Ƃ��E�K�v�ł���Εێ��N���[�����g���B
��w����
��w���Ŗ�i�G�^�m�[���j���\����Ɏ��A�܂��w��ɂ��肱�݁A�肪��������܂Łi15�b�ȏォ���āj��w�S�̂ɂ��肱�ށB�肪����Ă���Ƃ��͎�̂ق������ʓI�B
������
�p�ɂɎ��G���ꏊ��1��1��ȏ�A�E�ʊ����܁i��܁j�A�Z�x60���ȏ�̃A���R�[���A�Z�x0.02�`0.05���̎������f�_�i�g���E���̂����ꂩ��p���Đ@�����ł���B
��E��w���ł̂Ȃ��E���E�ǂ������?�H�i ��{�j�߁@2020/9/2�j
�����\�h��
�����͊����҂̊P�₭����݁A�ċC�ɂ���ĕ@�`����t�i�j����юU���āA���̔�����@�Ȃǂ̔S���ɂ����Ƃł�����B�͑傫���̂ł����������b�łQ���ȓ��ɗ�����B�A�ׂ����i�G�A���]���j�͐��b���琔���ԂQ���ȏ��܂ŕY���Ă���B�\�h�@�͊P�G�`�P�b�g���s���E�}�X�N������A�ߋ����ʼn�b�����Ȃ��A���C���悭����Ȃǂ�����B
�}�X�N
���o�Ȃ��悤�ɂ���ړI�ƃE�C���X���z�����ނ��Ƃ�h���ړI�����邪�A�O�҂���Ȍ��ʂŁA��҂͌���I�i�K�ɕs�D�z�}�X�N��N95�}�X�N������ƌ��ʂ���j�B���C�̈����ꏊ�A�ߋ����i�P���ȓ��j�ő吺���o�������ꍇ�Ȃǂ̓}�X�N��t���Ă��Ă��������X�N�͍����B�}�X�N�̑f�ނ͑��w�̕s�D�z���]�܂����B���_�ő��w�̕z���i�Ȃ����|���G�X�e���j�A�E���^�����͐��\�͂��Ȃ���B
��d�}�X�N�͕z��E���^���}�X�N���ƈꖇ�̕s�D�z�}�X�N�ɗ��B��d�}�X�N�ɂ���ꍇ�͕s�D�z�}�X�N�̏ォ��傫�߂̃}�X�N���B���悤�ɑ������A�s�D�z�}�X�N�Ɗ�Ƃ̌��Ԃ��Ȃ����悤�ɂ���Ɗ����h�~���ʂ������Ȃ�B���K����D�悷��Ȃ甧�ɕ��S�̂Ȃ��z�}�X�N���̏ォ��s�D�z�}�X�N������悤�ɂ���B�s�D�z�}�X�N�̂Q�d�͋�C��R���傫���Ȃ艡����̘R�ꂪ�����Ȃ�̂ł��܂���ʂ��Ȃ��B
�}�X�N���p�ɂ��V�^�R���i�̊����h�~���ʂɂ���
Effectiveness of Face Masks in Preventing Airborne Transmission of SARS-CoV-2
�i�����j�������ɂ�����E�C���X�����̗\���Ƃ��̑� 2021�N3��4�� �L�ҕ��� ���\������d�}�X�N
�R���i�E�C���X�����Ɋւ��錤�� �`�}�X�N�̌��ʂƉ̏����̃��X�N�����`
�����ŐV������E���^���}�X�N��̖{���̃��o��
�t�F�C�X�V�[���h�E�}�E�X�V�[���h�F
�t�F�C�X�V�[���h�͊�ɔ����ڂ�����Ȃ����ʂ����邪�A�����Ǒ�Ƃ��Ă̓}�X�N�����B�}�X�N�̒��p�̍���Ȑl���g�p����B�܂��l�Ƌߋ����Őڂ�����Ől�Ƃ̊ԂɃA�N������r�j�[���V�[�g���u���Ȃ��ꍇ�Ɏg�p����B���̏ꍇ�͕s�D�z�}�X�N�p����B�}�E�X�V�[���h�͊����Ǒ�Ƃ��Č��ʂ����܂�Ȃ��B
�V�^�R���i�� �@�t�F�C�X�V�[���h�E�}�E�X�V�[���h���Ăǂ��Ȃ́H�i��{�j�߁@2021/5/8�j
���C
���C�̈����ꏊ�͊������X�N�������B�Q�����̑����ł��邾���J���ĘA���I�Ɏ����ɋ�C��ʂ��B�P�������������Ȃ��ꍇ�́A�h�A���J���邩�V���ǂ̍����ʒu�ɂ��鑋��lj��ŊJ����B
�u���C�̈�������ԁv�����P���邽�߂̊��C�̕��@
�_�C�L���@���Ȋ��C�̕��@�@�I�t�B�X�E�X�ܕ�
�t�B�W�J���f�B�X�^���X
�����I�����B�R���i���E���W�E���ځj����B�l�Ƃ̊Ԃ��P���ȏ�i�ł���Q���j�Ƃ�B���������Ȃ��ꍇ�́A�d������邩�A�}�X�N���𒅗p����B���C�̈����ꏊ�ł͋������Ƃ��Ă��Ă��������X�N�������Ȃ�B
������u���݉�v�ɂ����� �W�c��������i2020�N10��23���j
Two metres or one: what is the evidence for physical distancing in covid-19?
�������ɂ�����E�C���X�����̗\���Ƃ��̑��i�����@2021/6/23�j
�G�A���]���E��C����
��C�����͂T�ʂ������̔j�z���ɂ�銴���B�G�A���]�������͔��ׂ������q���z���ɂ�銴���B�͂����ɗ����邪�A�G�A���]���͒����ԕY���B�G�A���]���̗��q�̒�`�͞B���Ŕj�����傫�ȗ��q���܂ށB
��C�������銴���ǂ͎O��ނ���B���j�̂悤�ɋ�C�����������Ȃ���ΓI��C�����B���]�̂悤�ɂق��̊����o�H������D��I��C�����B�C���t���G���U��V�^�R���i�E�C���X�̂悤�ɒʏ�͂��Ȃ������ʂȊ����Ŋ���������a���I��C�����B
Airborne transmission of SARS-CoV-2Science 16 Oct 2020
Transmission of SARS-CoV-2: implications for infection prevention precautionsWHO�@9 July 2020
���N�`���̎��
�����N�`���F��ʼn������a���́i�E�C���X�j�����������N�`��
�s�������N�`���F�s���������a���̂����������N�`���B�V�m�o�b�N�̃��N�`���͂��̃^�C�v�B
�E�C���X�x�N�^�[���N�`���F���Ő�����Ő��̃E�C���X�x�N�^�[�i�}��ҁj�ɍR������ς����i�X�p�C�N����ς����j�̈�`�q�iRNA�j��g�ݍ��A�g�݊����E�C���X�𓊗^���郏�N�`���B�^�щ��̃E�C���X���זE�Ɋ������A�זE���ŐV�^�R���i�E�C���X�̃X�p�C�N����ς���������B�x�N�^�[�E�C���X�͊������Ă��זE���ő����Ȃ��B�E�C���X���g���̂Ō����ǂ������Ă����Ƃ��������b�g�����邪�A��x�̓��ɓ���ƃx�N�^�[�E�C���X�ɍR�̂������_������B�A�X�g���[�l�J�i�x�N�^�[�F�`���p���W�[�A�f�m�E�C���X�j��W�����\�����W�����\���i�x�N�^�[�F�A�f�m�E�C���X�i26�^�j�j�̃��N�`���͂��̃^�C�v�B
mRNA���N�`���F�R������ς�����������������mRNA�̃��N�`���BmRNA�������ƕs����ł������Ă��܂��̂ŁA�����̖��ɕ�ݍ��ނȂǂ��Ĉ��艻���Ďg�p����B�V�^�R���i�E�C���X�̈ꕔ�i�R������ς��j�̐v�}�ł���mRNA���̓��ɓ���Ɛl�Ԃ̍זE�Ɏ�荞�܂�A�R������ς��ł���X�p�C�N����ς��������������B�X�p�C�N����ς��ɑ���R�̂�Ɖu�זE�����B�t�@�C�U�[&�r�I���e�b�N�A���f���i�̃��N�`���͂��̃^�C�v�B
DNA���N�`���F�R������ς����̉���z���������������DNA�̃��N�`���B��`�q���N�`���B�A���W�F�X�̃��N�`�������̃^�C�v�B
�g�݊�������ς������N�`���F�E�C���X�̍\�������ł���R������ς�����ʂ̍זE�ō�������N�`���B����`�����m�o�o�b�N�X��T�m�t�B�̃��N�`���͂��̃^�C�v�B
�V�^�R���i�ƃ��N�`�� �m��Ȃ��ƕs�s���Ȑ^��
�i�������j�V�^�R���i�E�C���X���N�`���̍��������ɂ������ā\mRNA���N�`���ƃE�C���X�x�N�^�[���N�`���̊�{
FDA Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine
CDC�@COVID-19 Vaccine: Helps protect you from getting COVID-19
(���@)�V�^�R���i���N�`���ɂ���
�i�����J���ȁj�V�^�R���i���N�`���ɂ���
�i�����J���ȁj�V�^�R���i���N�`���̕������^���ɂ���
���уi�r�iCoV-Navi�j�V�^�R���i�E�C���X�����ǂ�N�`���Ɋւ�������F����ɂ��͂�����v���W�F�N�g
�i���J�ȁj�R���i���N�`���i�r
�V�^�R���i�E�C���X���N�`��
�ڎ�̑����ē�
�V�^�R���i���N�`���ڎ��ɐV�^�R���i�E�C���X�����ǂƐf�f���ꂽ�Ǘ�Ɋւ���ϋɓI�u�w�����i����j2021/7/21
mRNA���N�`���̌���
�t�@�C�U�[�Ђ̃��N�`����f���i�Ђ̃��N�`���ɂ��ẮA���Ǘ\�h���ʂɂ��ẮA �Տ������ɂ����āA95%���x�̃��N�`���L�����������Ă���B�i2020�N12���@�A���t�@�������O�j
���O���Ŏ��{����Ă���u�w�������ɂ��A���X�Ɋ����\�h���ʂ����� �������ʂ�����Ă��Ă���B �A�����̉u�w�������ɂ����āA�����\�h���ʂɊւ��āA 90%��̃��N�`���L����������Ă���B
�ψي��̗��s���ɂ���ẮA�����\�h���ʂ��܂߂����N�`���̌��ʂɉe�����y�ڂ��\ ��������B
���݂̐V�^�R���i���N�`���̊����\�h���ʂ̃G�r�f���X�i�ߘa3�N6��23���j
�V�^�R���i �f���^�^�ψكE�C���X �����́A�d�lj����X�N�A���N�`���̌��ʂȂǁ@�����_�ŕ������Ă��邱��
�i���ߌ��u�@2021�N8��1���j
���N�`���ڎ킪�i�ޒ���
���퐶���͂ǂ̂悤�ɕς�蓾��̂��H
�i���ȉ���@�ߘa�R�N�X���R���j
�����ɉ����ču���ׂ��{��
���ȉ�w�W
�X�e�[�W�T�F�����҂̎U���I�����y�ш�Ò̐��ɓ��i�̎x�Ⴊ�Ȃ��i�K
�X�e�[�W�U�F�����҂̑Q���y�ш�Ò̐��ւ̕��ׂ��~�ς���i�K
�X�e�[�W�V�F�����҂̋}���y�ш�Ò̐��ɂ�����傫�Ȏx��̔���������� ���߂̑Ή����K�v�Ȓi�K
�X�e�[�W�W�F�����I�Ȋ����g��y�ѐ[���Ȉ�Ò̐��̋@�\�s�S������邽�� �̑Ή����K�v�Ȓi�K
�V�^�R���i�E�C���X�����Ǒ����ȉ�̒ɂ��� �ߘa�R�N�S���P�T���i�j
��v�s�s�l��10���l������E�z����10������������Ґ�����
�����g��\�h�K�C�h���C��
�N���X�^�[��
�u�����ҁE�ڐG�ҁE�����A���E�N���X�^�[�A���͐��䉺�ɒu���Ă�������K�͂Ȓn�旬�s�ɂȂ���Ȃ��v�Ƃ����V�^�R���i�E�C���X�����ǂ̓����ɂ���B�����҂����������セ�̊����o�H��ǂ��Z���ڐG�ғ����u�������肻�̌�����T���Ă����ϋɓI�u�w�����B���̒����͂�������T���ɖ𗧂Ă�B�����Ґ��������Ȃ�ΐϋɓI����s�������Đ��Y�������炷�i0.5�ȉ��j�B
COVID-19�ւ̑�̊T�O�i2020�N3��29���b��Łj
�ی��t�̂��߂̐ϋɓI�u�w�����K�C�h �m�V�^�R���i�E�C���X�����ǁn
���H�X�ɂ����銴����`�F�b�N���X�g�̏���� �N���X�^�[�����Ƃ̊֘A�ɂ��Ă̒��� ��43��V�^�R���i�E�C���X�����Ǒ�A�h�o�C�U���[�{�[�h�i�ߘa3�N7��14���j�@�����S
�����ǐ������f��
��{���Y��R0
�����ǂɊ�������1�l�̊����҂��A�N���Ɖu�������Ȃ��W�c�ɉ�������Ƃ��A���ς��ĉ��l�ɒ��ڊ��������邩�Ƃ����l��
�������Y��Rt
�Ɖu�l����s�������ȂǑ��̍Đ��Y���B1���傫���Ȃ犴���Ґ��͑��債�A�P�����Ȃ猸������B�w�����I�ɑ�������̂ŁA���{�̃N���X�^�[��ł�0.5�ȉ��ɂ��邱�Ƃ�ڕW�Ƃ��Ă����B
�����Ǘ��s�̗\���F�����ǐ������f���ɂ����� ��ʓI�ۑ�
�ڐG�@��̌y��
�����g��̊댯�������܂��Ă�����l�Ɛl�̐ڐG�@������炷�ϋɓI�������B
��̓I�ɂ̓K�C�h���C�������炵�Ă��Ȃ���ނ̒��s�����H�X�̋x�Ɨv���A�l���W������ό��n�̎{�ݓ��ɂ�������ꐧ���A�O�o���l�̗v���A ���������ړ��̎��l�v���ȂǁB
Rt2�̏ꍇ�A�ڐG�팸8����Rt0.4�ɁA6���팸��1.2�ɂȂ�B���݂̎����Đ��Y���ƐϋɓI��ł��̒��x�ڐG�@��팸�ł��邩�ŏ����̊����Ґ����ω�����B
����z�肳��銴���Ƒ�ɂ��� �ߘa�Q�N�W���V���i���j
�R�~���j�e�B ���r���e�B ���|�[�g
���o�C����ԓ��v�S����v�G���A�̐l��������
���_�u�w�ҁE���Y���̒���-�V�^�R���i���炢�̂������!
�u���H�X�̐��������ł�1�����Ŋ����҂͌���Ȃ��v 8�����������J�ȁg����J�h�̃V�~�����[�V���������J�i2021/1/5�j
�ً}���Ԑ錾�����ʂ��グ�邩��������2�̕ω��@8�����������Y�܂���ϐ��i2021/1/5�j
V-RESAS�@�V�^�R���i�E�C���X�����ǂ��n��o�ςɗ^����e���̉���
Agoop�@�V�^�R���i�E�C���X�g�U�ɂ�����l���ω��̉��
�⏞�E���t��
Go To
(�ό���)Go To �g���x�����Ɗ֘A���
�i�_�ѐ��Y�ȁjGo To Eat�L�����y�[��
�Y�s��/ �m���E�C���X/ �V�^�C���t���G���U/ MERS(�����ċz��nj�Q)/ �}�X�N/
��@�Ǘ�[��C�g���t�n�k��E���q��]